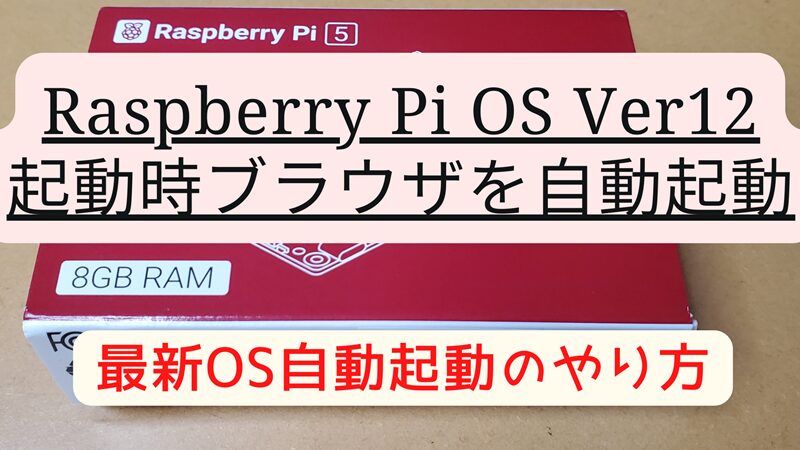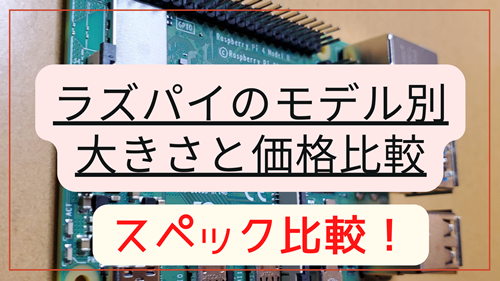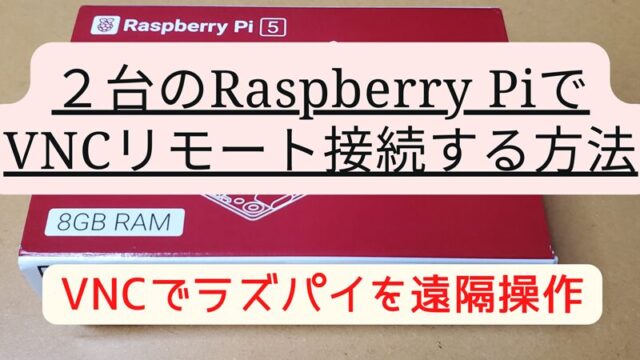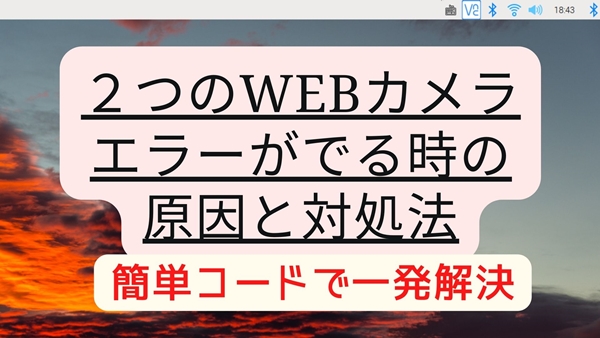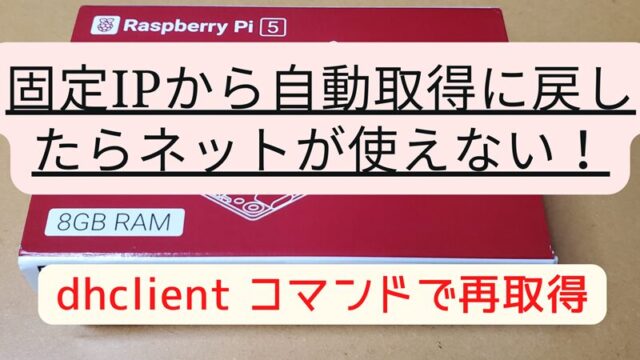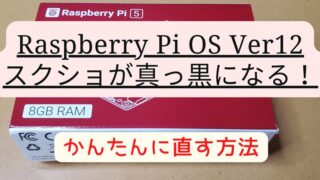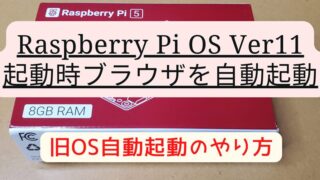Raspberry Pi OS Bookworm(バージョン12)で「起動時にブラウザを自動起動する」方法
〜 autostartが効かない時のsystemd活用ガイド 〜
この記事では Raspberry Pi OS Bookworm(バージョン12) を使って、
「電源を入れたら自動でブラウザを立ち上げる方法」を解説します!
Bookworm(バージョン12)では、
よく使われている『 autostart 』ファイル での自動起動が動かなかったため、
『systemd』を使ってブラウザを自動起動する手順を紹介します!
【記事内にアフィリエイトリンクが含まれています】
『systemd』ってなに?
『systemd』 は、簡単に言うと
「パソコンの中でアプリや機能を自動で起動・管理してくれるシステム」です。
ラズパイの電源を入れたとき
「いつ・どのアプリを・どんな順番で動かすか?」をsystemdが
コントロールしています。
【例えばこんな流れ】
①電源を入れる
②画面(デスクトップ画面)が立ち上がる
③「ブラウザを起動する命令」も自動で動く
この「順番どおりに動かす役割」をしているのがsystemdなんです。
つまり「Raspberry Piの自動実行マネージャー」だと思えばOK!
autostartがうまくいかないときでも
systemdを使えば「確実にブラウザを自動起動」できます。
Raspberry Pi OSの主なバージョン
Bookworm VERSION_ID=”12″の画面はこんな感じ。

自分のラズパイのバージョンがわからない人向けに
最新のOSバージョン一覧も載せておきます。
<2025年5月時点での「Raspberry Pi OS のバージョンと種類」>
| コードネーム | VERSION_ID | Debianベース | リリース時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Stretch | VERSION_ID=”9″ | Debian 9 | 2017年8月 | 古い、サポート終了済み |
| Buster | VERSION_ID=”10″ | Debian 10 | 2019年6月 | 古い、セキュリティアップデート終了済み |
| Bullseye | VERSION_ID=”11″ | Debian 11 | 2021年11月 | 互換性が非常に高い |
| Bookworm | VERSION_ID=”12″ | Debian 12 | 2023年10月 | 最新バージョン |
【ポイントごとにわかりやすく!】
Stretch(ストレッチ)
→ かなり昔のバージョン。すでにセキュリティサポート終了。使うのは危険。
Buster(バスター)
→ 2023年で公式アップデート終了。今から使う理由はあまりない。
Bullseye(ブルズアイ)
→ まだ安定性が高く、古いソフトや機器とも相性が良い。
「実験用」「古い機材と接続する人」なら今も使う価値あり。
Bookworm(ブックワーム)
→ 最新&公式おすすめバージョン
セキュリティも最新。新しい機能も使える。
ただし「設定方法が少し変わった部分」もあるので注意(今回のsystemdもその一例!)
起動時にブラウザを自動起動する方法
手順1:systemdサービスファイルを作成する
まずは 自動起動用のファイルを作成します。
ターミナルを起動して、
起動ファイルを作成するコマンドを入力します。
【起動ファイル作成コマンド】
sudo nano /etc/systemd/system/open_browser.service
【起動ファイルの内容】
ここでは、ブラウザは『YAHOO!JAPAN』を自動起動するスクリプトにしています。
下記の内容をそのまま貼り付けます
[Unit]
Description=Open Browser on Startup
After=graphical.target
[Service]
Environment=DISPLAY=:0
ExecStart=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs https://yahoo.co.jp
User=pi
[Install]
WantedBy=graphical.target
<起動ファイル作成画面>
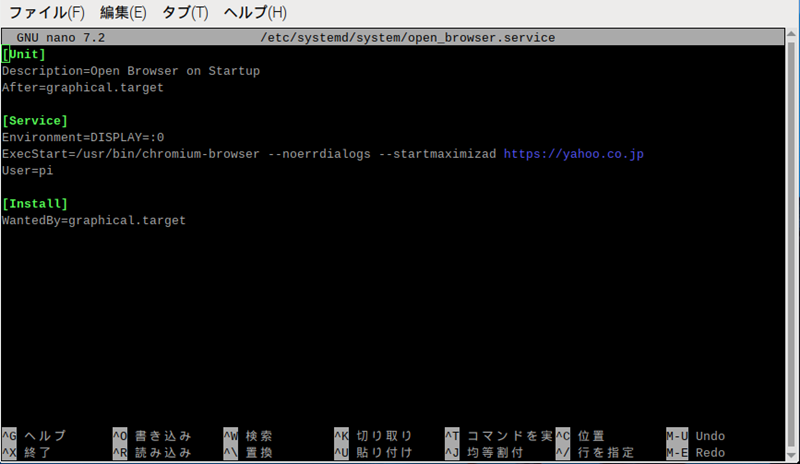
https://yahoo.co.jp の部分は、
自動的に開きたいWebサイトのURLに変更してください。
保存して閉じる操作
(Ctrl + O → Enter → Ctrl + X)
保存します。
<補足>
ウィンドウサイズは自由に変更できます。
サイト指定する前の部分にサイズ指定するだけで出来ます。
【ウインドウサイズを指定する】
ExecStart=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --window-size=1200,800 https://yahoo.co.jp
ウィンドウの位置を指定する方法
画面の左上(100,100)で幅1200高さ800に指定しています。
【ウインドウ位置を指定する】
/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --window-size=1200,800 --window-position=100,100 https://example.com
最大化にすることもできます。
【ウインドウサイズ最大化する】
/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --start-maximized https://yahoo.co.jp
自分の好きな位置、サイズできます。
手順2:『systemd』を有効化する
作成したファイルを 『 systemd 』に反映させて有効化します。
【『 systemd 』を有効にするコマンド】
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable open_browser.service
手順3:再起動して確認する
Raspberry Piを再起動します。
sudo reboot
再起動後は
デスクトップ画面が立ち上がった直後に、
Chromiumブラウザが自動起動して指定したページが表示されます!

これでばっちり!
まとめ
Bookworm(バージョン12)では
autostartが効かない場合は、
systemdで確実にブラウザ自動起動を設定しましょう!
【補足】ラズパイ5で、起動を速く・安定させたい人へ
Raspberry Pi5を使い
もっと速く・安定したマシンにしたい人は
→ 「SDカード」→「SSD」への変更がオススメ!
OS起動・ブラウザ起動が体感2〜3倍速くなります。
M.2 SSDを取り付ける場合、意外とケースが干渉しますので
干渉しないケースを選ぶのが重要です。